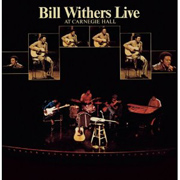明けましておめでとうございます。
最近更新が滞っていたこのブログも、今年こそはまた適度にアップしていきたいと小さく心に誓った本日です。
っで、そんな今年の一発目はこの曲です。
長らく探していたのですが、やっと数年前の初CD化のものを手に入れることができました。
発売当初から知る人ぞ知る、“白いスティービー・ワンダー”の異名をとるヴァレンティさんのアルバムですが、ジャケットも素敵だよね。
全体を通して、スティービーというよりは、ニューソウル全般の影響がぷんぷんと。特にこの曲はその代表格かも知れません。
スティービーのような鍵盤とハーモニカの使い方にカーティスのようなホーンセクションと揺れるギター。ワウギターもいいけれど、とくにカッティングギターは私のツボです。ぜひ、練習してみたいって久しぶりに思わせてくれました。
メロディラインもとても綺麗で、甘くて、でも芯の強いメロは変な異名がなければ本当にヒットしたんではないかと思うほど。大好きなメロディですね。
しかし、聴けば聴くほど、鬼才 トッド・ラングレンとの共通点が見えてくるのは私だけでしょうか?ソウル好き、美メロ、アレンジの完成度の高さ、B級路線など・・・そんな彼らが好きな私も所詮B級路線なんだろうなぁ。