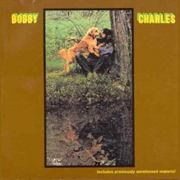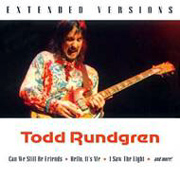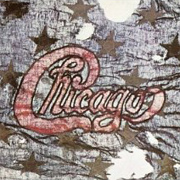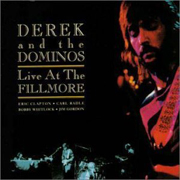
実は、クラプトンが好きと言い放っていた私ですが、このアルバムは最近まで聴いたことがなかったんです。
理由は、もともとの「イン・コンサート」ってアルバムをアナログで所有していて、その録音状態にうんざりしていたから。日本版であることも災いして、かなりモコモコな音で、とても4ピースの緊張感を感じるまでにいたりませんでした。
ところが、先日、たまたま中古で発見したこのアルバムを聴いてみてどうでしょう、ライブの臨場感が生々しく伝わってくるではありませんか。
特にこの曲ではイントロのワウの音色からして生々しい。ギターの音色も心地よく、リズム隊の音も輪郭がくっきりしているので非常にリアル。
ボーカルを取りながらソロでは泣きのリードギターを弾きこなすクラプトンを目の前にして聴いているようで、技量や充実感も伝わってくるかのようです。
オールマンのライブも90年代に出たリミックス版の方が好きだったけど、ドミノスの場合もそれとまったく同じ印象でした。なんだかこの2つのアルバム、いろいろな意味で似てるなぁっと感じるのは私だけでしょうか?